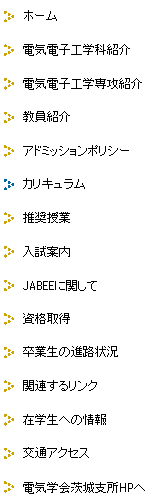
|
電気電子工学科の教育カリキュラムは、電気エネルギーシステム、パワーエレクトロニクス、集積回路、光情報、光通信、回路・情報システムなどの階層構造をなす基礎学問の十分な理解が得られるように配慮した構成になっています。 |
|
4 |
|
年生 |
|
3 |
|
年生 |
|
電気エネルギーの発生から有効利用までの電気エネルギー技術を中心に学びます |
|
集積回路から情報通信システムまでの情報エレクトロニクスを中心に学びます |
|
・電気エネルギーシステム ・パワーエレクトロニクス |
|
・光情報システム ・コンピュータ応用 |
|
2 |
|
年生 |
|
1 |
|
年生 |
|
カリキュラムの特色 |
|
1年次の専門基礎科目である数学,物理,および電気回路等の講義を少人数教育で丁寧に教えるために2クラス同時開講しているのが最大の特色です.これは,専門科目を学ぶ上で不可欠な基礎学力を1年次にしっかりと身に付けてもらうためのものです.数学演習I,II,線形代数I,微分積分I,微分積分II,ベクトル解析と電磁気,電気回路Iの8科目を2クラス同時開講しています. 授業では,教員同士の連携を密にし,宿題や演習を必要に応じて行いながら,学生の学習支援を積極的に行っています.特に,数学演習Iでは,内容的には高校の数学の範囲を接続教育も兼ねてもう一度,確実に学び直すことを目指し,数学の学力の不十分な学生でも本プログラムに支障ないように配慮すると同時に,複素数を4週にわたり講義形式で行い,電気回路で用いる虚数単位の導入まで行っています.また,基礎電気物理入門の授業では,ブレッドボードと電子回路部品を用いて,種々の電子回路の組み立て,動作確認を行わせ,簡単な電子回路の作成を全員に体験させています. 2年次でも専門基礎科目である電気磁気学I及び演習,電気磁気学II及び演習,電気回路II,の3科目は2クラス同時開講し,少人数教育を行っています. 2年次開講の電気電子工学ゼミナールの授業では,地球温暖化問題に代表されるような地球規模での解決が必要な諸問題および技術者倫理などの諸問題を,インターネットなどを利用して調査学習させ,地球的視点からそれらの諸問題を考えることのできる能力を,プロジェクターを使った口頭発表,討論,レポートにより養成しています. さらに,基礎学力を身に付けていないために専門科目の講義を理解できなくなることを事前に防ぐために,1年次と2年次の科目のほとんどを必修科目および選択必修科目として準学年制を導入し,必修科目の修得単位数が基準以下の学生には高学年の授業を受講させない規制を課しています. 3年次からは電気システムコース,電子システムコースの2コースに分け専門知識を習得させています.特に,電気電子工学実験IIIでは,デザイン能力の育成を目指して,実験課題の調査・検討をグループで分担して行い,詳細な実験計画を立てた後に実験を行い結果をレポートにまとめるまでの自主性を重んじた実験を行っています. 4年次には各教員に学生2-4人が配属され,英語の論文や書籍等を読みプロジェクターで発表させる電気電子工学プレゼンテーションを行わせ,卒業研究では各人に与えられたテーマに関して,10月頃には中間発表を行わせ,2月に卒業論文の提出及び予稿作成,プロジェクターによる研究発表を行わせることを通じて,高度職業人としての実践力を身につけさせています. |
|
卒業研究と応用的な内容を学びます |
|
1教員あたり約4名の学生配属という少人数教育により、きめ細かな指導を実現します。また、これからの技術者(研究者)には、「説明する力」プレゼンテーション能力が必要とされます。電気電子工学の知識や技術力だけでなく、これらの能力をゼミ形式の講義や卒業研究を通じて、習得します。 |
|
大学院進学・就職 |
|
約半数の学生は引き続き大学院へ進学しています。 大学院ではより専門的な知識を習得できます。 |
|
2コースに分かれて電気電子工学に関する専門的な内容を学びます |
|
電気システムコース |
|
電子システムコース |
|
電気電子工学の基礎を学びます |
|
抽象的な現象の理解を深め、応用力を養うために少人数教育や演習を取り入れています。 |
|
共通専門 (計測・制御、電磁気、回路、物性・量子工学、半導体、情報・通信)電気システム・電子システム、各コースで必要な専門科目 |
|
電気電子を学ぶ上で必要な基礎科目を学びます |
|
高校ー大学の接続教育と演習を多く取り入れているため、スムーズに専門科目に移行できます。 |
|
専門基礎 (数学、物理、化学、電磁気学、回路、プログラミング)電気電子工学を学ぶために必要な基礎科目 |
|
茨城大学 工学部 電気電子工学科 |
